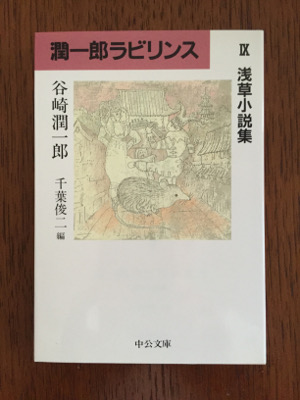ラビリンスは迷宮といういう意味であり、複雑に入り組んだものの比喩表現だ。
谷崎潤一郎は迷宮浅草に挑んだことになる。
この本には、『襤褸の光』『鮫人』『浅草公園』が収められているが、『襤褸の光』は短編、『浅草公園』は随筆であり、この本の大部分を占める『鮫人(こうじん)』は未完となっている。
『襤褸の光』は明治40年代、『鮫人』は大正7年の浅草公園を舞台にしている。
驚くことは、小説の大半が人物描写で占められているということである。特に顔の描写に力が入れれている。
2つの小説には共通点がある。それは、登場人物はみな浅草にやってきたということである。
『襤褸の光』に登場する若い女乞食も、画家に成り切れないAも成れの果てに浅草公園に落ちてきた人物であるし、『鮫人』の画家に成り切れない服部がたどり着いた地であり、歌劇団に属する人は、どこの生まれか育ちかはわからないが、浅草に寄り集まって生計を立てている人たちである。
著者は『鮫人』の中でこう言っている。
「怠け者で、金がなくて、意志が薄弱で、それでやはり贅沢な物質欲から自分を救い出すことが出来ない人々、そう云う人々がだんだんと社会の壓迫に追い詰められ、不平の餘り世を茶化したり拗ねたりする料簡になり、やけ糞半分から安価な享楽に溺れる為めに集って来る土地としては、浅草ほど究竟の場所はないのであるから。………
醜悪が醜悪そのまゝの姿で現れて居る浅草が、一番住み心地のいゝ場所だとも云えないことはないであろう。其処には下町の中心地や山の手にあるような虚偽や不調和がなく、醜悪がやゝともすると『美』に近い光を放って輝いて居る」
著者は、そんな素のままの浅草に惹かれ、相容れない要素が詰まった矛盾だらけの人物の顔に、浅草そのものを感じたのかもしれない。
心に残り続ける昭和のおかあさん
『浅草のおかあさん』